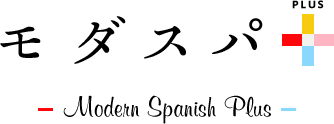「食の歴史はテクノロジーの歴史」と著者はいう。
「何を料理するか」を論じた書物は多いけれど、「何で調理するか」を論じた書物は少ないかもしれない。
本書では、料理道具の数々は、どのように発明され、改良されてきたのか、そしてそれらの登場や、改良・発展が、人々の暮らしや文化にどのような影響を与えてきたのかを、豊富なエピソードで解き明かす。
第1章 鍋釜類
第2章 ナイフ
第3章 火
第4章 計量する
第5章 挽く
第6章 食べる
第7章 冷やす
第8章 キッチン
紀元前の縄文土器から始まって、産業革命の産物として石炭・鉄が料理用レンジをもたらした話、ナイフの切れ味が現代のヒトの歯並び「被蓋咬合(ひがいこうごう)」をもたらしたという説など、話題は東西・歴史を問わず広範で、具体的で読みやすい。
どのページを繰っても、興味深いエピソードがある。
例えば第7章「冷やす」の項にある、フランス語「frigoriphobie(冷蔵庫恐怖症)」という言葉。
冷蔵庫は、販売者にとっては、売る商品の販売期間を引き延ばしてくれるものであるにもかかわらず、市場に入り始めた当初は、消費者も販売者も抵抗したのだという。冷蔵庫はチーズの本来の持ち味を殺す、冷蔵庫は食品貯蔵室で熟成させたものにはかなわないと考え、さらに「(販売者は)プライドを傷つけられたように感じた」と感じたらしい。
イギリスでも、質素を尊ぶ国民性から、あるいは、飲み物を冷たくするアメリカ人的嗜好を過度に恐れる心理から、第二次大戦後においても、イギリスで冷蔵庫を所有する世帯は2%にすぎなかったという。
ナイフの場合は、18世紀ごろから装飾品としての意味合いが濃くなり、現在のように切っ先が尖っていないものになった。
そのはじまりは、17世紀にフランスのリシュリュー枢機卿が、晩餐の席上で客が両刃ナイフの尖った切っ先を使って食後の歯の掃除をしている姿に肝をつぶして、屋敷中のナイフの切っ先をすべて丸くしたことからだという。
テクノロジーの発展がときとして、なぜそのような、ときに合理性と逆行するような進化の仕方をしているのかは興味深い。
このようなテクノロジーの発明や発展が、まがまがしいものとして、或いは、手仕事の作業に価値を置く立場からの反発によって、拒否反応を多く受けながらも、料理をする人間から最終的には圧倒的な支持を得て普及していく過程は本書に多く登場する。しかしその発展は、多くは料理に膨大な単調な作業を必要とする労働力の解放だったし、あるいは、消費者の所有欲を満たす(キッチンに美しく並ぶ銅鍋のような)ものだったりする。
そして、それらのエピソードを読むことで、本書は私たちに、どのような料理道具にも、それが「ある前」が必ずあったのだということを思い出させてくれる。
例えばどこの台所にもある1本の木製のスプーン、それが「テクノロジー」という言葉からは遠いものであっても、木目、形、価格など、より適切なニーズがあってそのような製品になったのかの理由が必ずあると説く。
時代がどんなに変わっても、料理というテクノロジーを抜きに私たちは生きられない。
火と手とナイフ。
これだけはいつも欠かせない。
「キッチンの歴史 料理道具が変えた人類の食文化」
原題 CONSIDER THE FORK
ビー・ウィルソン Bee Wilson (著), 真田 由美子 (翻訳)
河出書房新社 (2014/1刊)¥3,024
著者は74年英国生まれ。女性フードジャーナリスト。