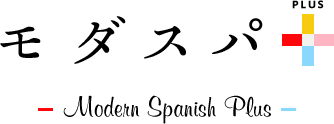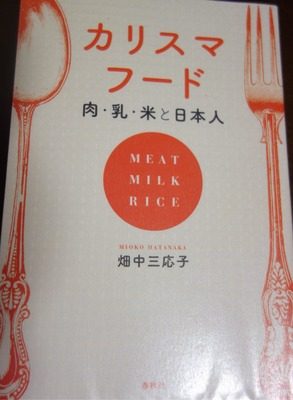「美味しさ(味わい)は、口ではなく、脳が創り出している。 その決め手は、口中から鼻に抜けるにおいであり、『においのイメージ』がパターンとして、脳で味わいを生み出す。」
本書は、嗅覚を研究する科学者が、風味と身体の関係についてさまざまな角度から論じたものだ。
内容は、人間が身体のどの部分でおいしさを感じ、風味として記憶するのか、逆に、風味がきっかけで呼び起こす記憶について、あるいは風味が脳を活性化させて食物の依存、肥満を引き起こす理由など広範な範囲にわたる。その広がりを見渡すという意味で貴重な本だ。
◆目次
◆はじめに:味わいは脳の創造物である
◆序文:新しい風味の科学「ニューロ・ガストロノミー」
◆第1部 鼻とにおい
第1章:においと風味の研究の革命
第2章:犬と人間の嗅覚を比べる(レトロネイザル経路に注目)
第3章:口が脳をたぶらかす
第4章:風味の分子
◆第2部 においを描く
第5章:におい分子の受容体
第6章:感覚イメージの形成
第7章:においの空間パターン
第8章:においは顔に似ている
第9章:においのイメージは点描画
第10章:イメージの強調
第11章:嗅皮質への注目
◆第3部 風味の創出
第12章:嗅覚と風味
第13章:味覚と風味
第14章:マウス・フィール(口中での質感)
第15章:視覚と風味
第16章:聴覚と風味
第17章:風味を生む筋肉
第18章:知覚系+行動系=ヒト脳風味系
◆第4部 風味が大切なわけ
第19章:嗜好と渇望
第20章:風味と記憶:プルースト再解釈
第21章:過食と肥満の原因
第22章:風味と栄養の神経経済学
第23章:ヒト脳風味系の可塑性
第24章:言語とのかかわり
第25章:意識・無意識とのかかわり
第26章:においと風味が人類を進化させた
第27章:胎児から老年まで
—————–
風味は食物が備えているわけではなく、脳が作り出すもの
まず、人は食べ物の味をどのようにして決めているかについては、「レトロネイザル経路のにおいが脳と結びついて決めている」という。
「レトロネイザル(後鼻腔)」とは、レトロ=後部、ネイザル=鼻腔で、後鼻腔を意味する。
口中香と呼ばれるレトロネイザルは、食べ物を噛んだり飲み込んだりしたときに、口の奥から鼻道へ至るにおい。著者はこのレトロネイザルと食べ物の味が合わさったものを「風味」と読んでおり、ヒトの身体(鼻とのどと口の位置)は、それを受容しやすいようにできているのだという。
それに対し、普通に鼻から嗅ぐにおいは「オルソネイザル(前鼻腔)経路のにおい(オルソ=前部で、前鼻腔)」。こちらの働きよりは、口の中から鼻に抜ける食べ物の香りの方が、「風味」として人の記憶に強く残るのだという。
味の知覚は「甘味、辛味、苦味、酸味、うま味」の5つであるというのは有名な話だが(最近の学会では、6つ目に「油脂の味」が提唱されつつあるとも聞くけれど)、その5種類しかないのに人の食べ物の好みが千差万別になる理由は、食べ物を口にした食物の風味は、においが…つまり脳が決めているからなのだという。
味が5種類しかない…と言われると、もっと千差万別な味があるのでは、といいたくなるのだけれど、その「千差万別」は、のどから上がってくる食べ物の香り、つまり風味ということらしい。
風味がきっかけで呼び起こす記憶については、プルーストの代表作「失われた時を求めて」の冒頭の有名なシーン、つまり、ハーブティに浸したマドレーヌの香りがきっかけとなって、幼少期の記憶が鮮明によみがえるときの描写について、「甘美な記憶」が脳でどのようによみがえっていったのかが、1章割いて分析されている。
ここで重要なのは、脳や神経のどの部分が動いて記憶をよみがえらせたかではなく、「甘美な記憶」がなぜ起きたかを知りたいと思う意思を仲介する前脳に、においと風味の情報が直接たどりつくという指摘だ。この動機付けが強力に行われると、過剰なほど食べ過ぎる、つまり、肥満あるいは薬物依存の原因にもなるという指摘は興味深い。本書ではそのプロセスについても論じられている。
具体的なエピソードの中でおもしろかったのは、ワインのテイスティングと評価に使われる言語についての記述だ。
ワインのテイスティングや評価は、においを言語で表現する難しさに直面する分野だが(本書ではそれを青黄赤で単純に分析できる「色」と比較して、絵画を評価する難しさにたとえていた。ことばにするのに複雑すぎるという意味だ)、ワインの味わいを科学的に分析する研究者(アン・ノーブル氏)は、自分のワインの評価のために、「ワイン・アロマ・ホイール」という、ワインのアロマをあらわす用語を三重の同心円にまとめたものを作成していたという。
一番内側の円の最も一般的な用語「フルーティー、土臭さなど)から初めて、次の円にはより具体的な用語(ベリー系、柑橘系など)、一番外側にはさらに特定的な用語(各種果実、フレーバーなど)とアロマを表現する用語が列挙してあるという。感じたものを階層的に分類するための、論理的なしくみというわけだ。
どういう味だったかを説明したいと思い、言語を用いる、その言語があってこそ風味を感じるという、ヒトにしかできない行為がとても貴重なものに見えてくる。
そして、「風味」を生み出す調理こそが、人間を人間たらしめている決定的な特徴であるという本書の指摘も、そこまで読むとすとんと腑に落ちるのだ。
「美味しさの脳科学:においが味わいを決めている」
ゴードン・M・シェファード(著), 小松淳子(翻訳)
発行 インターシフト(発売 合同出版)
¥2,450+税
2014/4/30