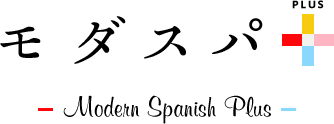フードジャーナリストで「コルドン・ブルー」でも学んだことのある英国人の著者が、日本の食を食べつくすために2か月の休暇を取り、一家で日本をおとずれる物語。
旅のきっかけは、著者が辻静雄の名著「Japanese cooking:A simple art」(1980)を日本人の友人の料理人にすすめられて読んだことだった。読み終わったその日に、彼は日本行きの航空券を4枚予約し、そこから一家四人の珍道中が始まる。
行き先は、東京、北海道、京都、大阪、福岡、そして沖縄。
銀座の会員制料理店「壬生」をはじめとした、日本の食文化を体現しているような最高級の料理店から、新宿歌舞伎町の怪しげな焼き鳥屋に至るまで、著者は雑多な日本文化に触れ、先入観なく食べ、率直な感想を残し、日本の食の特長を探しだそうとする。
著者が訪れた場所は料理店だけではなかった。
料理専門学校(東京の服部と、大阪の辻調の両方を訪れているのはすごいと思う)、相撲部屋、新宿の「忍者屋敷」、「ビストロSMAP」のスタジオ、札幌や大阪の卸売市場、昆布を扱う南やかべ漁業協同組合、日本酒の醸造所、味噌蔵、新横浜ラーメン博物館。このラインナップを見るだけで、どんな面白い旅になるかは想像できる。(実は原書「Sushi and beyond」には、MSGの取材のために味の素を訪れた場面も出てくるとのこと。これは続編「英国一家、ますます日本を食べる」に収録された。レビューはこちら)
視点は日本文化になじみのない人だからこそ気づくような鋭さがあり(怪しげな焼き鳥屋でも、焼き鳥を小さくして焼きむらをふせいでいるという工夫に着目していた)、表現にはユーモアと時折まじる皮肉とあたたかみがある。
この「物語」を面白くしているのは、「訳者あとがき」にもあるように、著者と一緒に同行した家族の存在である。妻のリスンと二人の息子、6歳アスガーと4歳のミエルは、力士の姿を美しいと見とれたり、自分の顔より大きなカニにびっくりしたり。著者一人での旅行よりもさらに視点が広がる役割を果たしている。
いち読者としてちょっぴりうらやましかったのは、日本人でもなかなか行けないような場所をずいぶん訪れていること。服部校長に連れられて行った日本料理アカデミーの第1回「日本料理コンペティション」関東甲信地区大会もそうだし、一見さんお断りの「壬生」や人気TVスタジオの舞台裏などもそう。でもそれは、取材の際に言葉や習慣の壁で苦労する分と引き換えの、余得というようなものなのだろう。
この本、2013年4月に刊行されてから、売れているらしい。
続編「英国一家、ますます日本を食べる」も出たし、柳の下の類書も出た。
この本が「異邦人が日本文化の良いところを発見していく」という「売れる物語」の王道に位置するという文脈で読めば、この人気も納得のいくところかもしれない。
「英国一家、日本を食べる」(亜紀書房翻訳ノンフィクションシリーズ)
原題 ”Sushi and Beyond: What the Japanese Know About Cooking”
マイケル・ブースMichael Booth (著), 寺西 のぶ子 (翻訳)
亜紀書房(2013/4/刊)
¥2,052