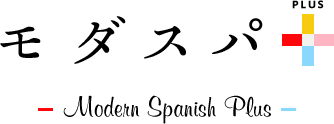日ごろ私たちが自宅のキッチンやレストランで触れる料理、例えば、野菜を炒めたり、パンを焼いたりする。そのときの食材の反応はすべて「化学反応」である…と言われると私のような文系的かつアナログ人間にはかなり違和感があるのだけれど、確かにそうである。そうして出来上がったものはだから「食事」でもあり、「化学反応性生物」であるともいえる。
本書は、その定義を確認するところから始まる。
本書は、料理を物理学、化学、生物学、工学などの視点から解き明かしたもの。「分子料理」というときの「分子」には、料理を「科学的視点」から見ているというニュアンスがこめられている。出来上がりを予想して作るのも料理なら、化学から導かれた数字で調理された食材だって料理といえるはずだ。それらは科学的視点かアナログ視点かという二択ではなく、不可分でつながっている。
目次
1.「料理と科学の出会い」の歴史
料理人が「科学」に出会うとき
科学者が「料理」に出会うとき
「料理と科学」の未来
2.「料理をおいしく感じる」の科学
料理のおいしさを脳で感じる
料理の味とにおいを感じる
料理のテクスチャーと温度を感じる
3.「おいしい料理」の科学
おいしい料理を構成する基本四分子
おいしい料理のカギを握る分子
調理における反応と物質の三態
4.「おいしい料理をつくる」の科学
おいしい料理をつくる前に
調理道具
調理操作
5.「おいしすぎる料理」の科学
「おいしすぎるステーキ」の分子調理
「おいしすぎるおにぎり」の分子調理
「おいしすぎるオムレツ」の分子調理
「料理のテクスチャーと温度を感じる」の項で書かれている、テクスチャー(触覚による風合い)についての言及は興味深い。これも「おいしい」と感じる感覚と切り離せないものだという。
唇や口の中やのど、歯などで感じるテクスチャーを、味や香りの「化学的なおいしさ」に対して「物理的なおいしさ」とし、食べ物の種類によってそれぞれの重み、重要性が変わっているとする。
例えば、クッキーなどさくさくした食品は「物理的なおいしさ」、ジュースなどテクスチャーの比率が少ないものは「化学的なおいしさ」の影響力が強い。本書の解説を読んで行くと、日ごろ自分が何気無く食べているものを、そうやって感覚的に分けていくというか、感覚を微分していく感覚におちいる。確かに、おいしいとひと口に言っても、その中身はそうやって分けられるということだ。
面白いのは、同じ食材であっても、テクスチャーが違うと、受け取る人間の感じ方が異なるということだ。
例えば、あんこの場合だと、固形のあんよりお汁粉の方が甘味を強く感じるのだという。だから、固形のあんこよりお汁粉にするときの方が甘味はずっとおさえられているらしい。つまり、「テクスチャーが味を変える」といえるのだ。味を変える、というか、人間の感じ方が変わる、ということだろう。
どんぶりを無心でかきこむ幸せ…
これ以外にも、建築と料理の共通性、どんぶりを無心でかきこむときに「クライマーズ・ハイ」に似た高揚感を感じるプロセス、香りの分子が似た食材は香りが似ること(例えばキュウリとアユなどは香りの分子が似ているのだそうで、だから合わせるとおいしいわけだ)、その共通する香りを持つ食材どうしをあわせると統一感が出る(だろう)という「フードペアリング」の発想(これは http://www.foodpairing.com というサイトで調べられる)など、化学的なアプローチで料理を見ると、思いもよらないところに、食材の組み合わせや「おいしい」と感じるトリガーがあるものだなと感じる。
著者の石川氏は分子食品学・分子調理学・分子栄養学の研究者で、学生時代は、アイスクリームの自作が好きな「料理男子」でもあったという。冬の深夜にアイスクリームを大量に作りながら、「滑らかな舌触りのアイスを作るために、黄身の乳化性などを分子レベルで考えないといけない」と感じたというから、そのころから発想方法がすでに科学だったのだ。(著者のブログ「夜食日記」もぜひ。)
料理で起きる化学反応や、料理を食べたときの人間の生理的反応から料理とは何か、おいしさはどこにあるのかを掘り下げるこのような分野は、今日、料理について考えるときには知っておいた方がいい…というか、避けて通れない分野だと思った。
本書冒頭には、ここ10年の、フェラン・アドリアやエルヴェ・ティスの試行についても簡潔にまとめられていて、分子料理について概観を理解するのに役立つと思う。
料理と科学のおいしい出会い (DOJIN選書: 59)分子調理が食の常識を変える
石川 伸一 著
化学同人 (2014/6/10)
本体1,700円+税