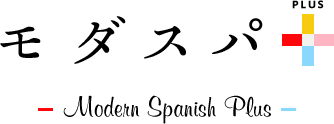どれほど豪華であっても、昨日オープンした店に「グランドメゾン」という称号がそぐわないように、「グランドメゾン(あるいは、グランメゾン)」と呼ばれる店には、必ず歴史とエピソードがある。
日本でそのように呼ばれる店の筆頭にあがるだろう銀座の「ロオジエ」は、1973年に銀座の資生堂会館にオープン、前身の、ソーダファウンテンを出した資生堂パーラーの歴史を加えれば、その歴史はゆうに100年を超える。
本書は、その歴史をひもとくとともに、その「メゾン」を作る「もの」を通じて店全体の魅力を明らかにする。
著者の橋本麻里氏は、日本美術を主な領域とするライター・エディター。レストランの核心である料理の解説をあえて巻末にまわし、カトラリー、グラス、リネン、厨房、建築などの「もの」の具体的なエピソードからレストランの魅力を語るという「ある意味『非常識』な本」(「エピローグ」より)が出来上がった。
「もの」を中心に語られている本書だが、読後に最も印象に残るのは、「もの」の写真の美しさではなく、収録されたスタッフの多数のエピソードと言葉である。
その最も重要なものはやはり86年に就任したジャック・ボリーシェフだ。ボリーシェフの就任がロオジエのすべてを変えた結果、いまのロオジエがあるのだというのがよくわかる。
ボリーシェフは就任3日で辞表を出し、資生堂から引き止められて「好きにおやりなさい」とフリーハンドを与えられたあとは、厨房の改善から内装、レイアウト、装花まですべてをあらためたという。
ロオジエが今のような連日満席の店になったのは、それからあとだ。
ボリーシェフは在任中、「料理は4割、サービスが6割」と言い、厨房では「普通に」を徹底させた。
ボリーは全スタッフに対して、二言目には「普通に」と言い続けた。「以下」は論外。「以上」もトゥーマッチ。プロフェッショナルとしていかなるミスもせず、パフォーマンスもせず、バタつくことも怒鳴ることもなく、淡々と始まって終わるのが、最高の料理を出すことの基本的な「構え」となる。そしてその「普通」を毎日毎日続けることが、もっとも難しいのだ、と。(第2章「受け継がれる最高品質のおもてなし」)
テレビ局が厨房を取材しても、最も忙しい時間帯でも厨房はアイコンタクトやわずかな動きだけで仕事が進み、「シーンとしていた」という。思うような映像が取れず、困惑するテレビ局のスタッフの顔が目に浮かぶ。
「普通を毎日続けることがもっとも難しい」という言葉からは、私たちが現在のロオジエを訪れるといつも感じられるような、いつも変わらない、尊大でも卑屈でもない、淡々として人間的な雰囲気を、スタッフ一人ひとりが作っているのだとわかる。現在考えうる最高の品質で選ばれた「もの」や料理は結局すべて、このポリシーを持ったスタッフたちによって支えられているのだ。

本書に掲載されている、ロオジエを支える全スタッフ。最前列に元シェフ、ジャック・ボリー氏の姿が見える。
——
本書の冒頭でも書かれているように、現代の食の世界で大きな力を持っているのは、料理人の名前である。
ミシュランガイドやベストレストラン50では必ずレストランの名前とシェフの名前がセットで語られるように、シェフの名前は、現在、レストランを語るときに外すことができない。
著者はその現状を肯定した上で、「外食の楽しみや食文化が、一個人の能力が及ぶ範囲に限定されてしまうのは、いささかもったいない気がする」と述べる。
人に収斂されるレストランの主流な現代への、一つのアンチテーゼとも読める。
ロオジエ本に書いたように、とかく料理と料理人が評価の中心となってしまう昨今、「外食の楽しみや食文化が、一個人の能力が及ぶ範囲に限定されてしまうのは、いささかもったいない気がする」のですよね。「美味しい料理」はそれなりに個人の力で実現できても、食文化という側面では限界あるから。
— 橋本麻里 (@hashimoto_tokyo) 2015, 6月 22
グランメゾンに歴史が必要ならば、レストランが毎日新しくオープンするような、移り変わりの激しいいまの時代は、グランメゾンには厳しい時代だ。
人の嗜好は変わりやすい。お金の出どころも、流れも変わりやすい。しかも、昨日オープンしたレストランにも、短期間での資金回収が求められる。
いまの時代、グランメゾンの歴史に変わるものは、シェフの経歴になった。
昨日オープンしたレストランでも、シェフの経歴から、おいしくなる店かどうかある程度判断できるようになったと思う。それは、短期間で結果を求められるいまの時代には沿うものだ。SNSを通じてシェフの顔が見えやすくなったのもそうだし、ミシュランが「評価するのは皿の上」と方針転換したことも、「料理がすべて」な時代を後押ししたと思う。
だから、建物、内装、器具、道具、装飾品、料理とすべてのものの総合力で勝負しているグランメゾンは、いかにそのお勘定が高かろうと、今は生き残るのが難しい時代に違いない。
「社会がフラット化し、文化をパトロネージュできる旦那衆が消えた後では、時に企業がその責任を担わなければならない(「はじめに」より)。
ロオジエにとってその責にあるのはもちろん資生堂である。本書でも指摘されている通り、ロオジエの存在は、収益という点では決して母体の資生堂に大きく寄与しているわけではない。
レストラン経営とは、良心的にやればやるほど利益の上がらない業種だという。だからこそ、それを維持し続けている店と資生堂には、いくらリスペクトしても足りないと思う。
一軒のレストランは、ひとつの文化なのだ。
THE STORY OF L’OSIER 最高のレストラン「ロオジエ」最上のおもてなしの秘密
橋本 麻里著
<内容>
第一章 日本最高峰のフランス料理店であり続ける理由
第二章 受け継がれる最高品質のおもてなし
第三章 五感すべてを喜ばせる料理
<発行>株式会社マガジンハウス
<発刊日>2015年3月26日
<定価>1,400円(税別)
<仕様>A5判 128ページ