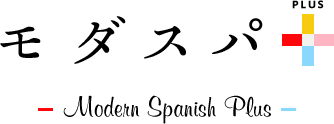★2023年6月21日追記★
本日発表された2023年「世界のベストレストラン50」において「セントラル」が1位を獲得しました。
2002年に開始され21回目の同賞で初めての欧州・米国以外の地域からの世界1位、おめでとうございます。
「世界のベストレストラン50」で2022年に世界2位を獲得したペルーの名店「セントラル」のシェフ、ヴィルヒリオ・マルティネス氏の手がけるレストラン「マス(MAZ)」が2022年7月、東京に開業した。
マルティネス氏は2009年、32歳で「セントラル」を開業、2017年には、リマから1000kmほど離れたモライ遺跡に研究所「マテル・イニシアティバ」を開設し、レストランとともに、ペルーの自然と生態系について研究・発信してきた。
東京店を任されたサンティアゴ・フェルナンデスさんはベネズエラ出身、「セントラル」に6年間勤務し、同店でヘッドシェフをつとめた人物だ。
ペルーとは自然も気候も生態系も何もかもが異なる日本で、「セントラル」のコンセプトを伝えるにはどうすればいいのか。フェルナンデスさんはペルーから遠い日本の地で、ペルーに馴染みの薄いゲストを相手に、日本食材を用いてペルーを表現するという難しい役割を担う。
「マス」の料理は本国「セントラル」の料理とはかなり異なっている。
ペルーの地域は大きく次の3つ、海岸地帯、山岳地帯(アンデス山脈)、森林地帯(アマゾン地域)に分けられ、それぞれ異なる気候帯を持つ。そして、日本のような季節という感覚はなく、その役割を高度が担っているという。
「マス」では、ペルーの自然を、高度ごとに分けて9つの生態系・9皿の料理であらわしている。
(MBSL=水深、MASL=海抜)

①冷たい海 -5MBSL(水深5m)
貝 – スピルリナ – 海ぶどう
3種のアミューズ。
意表を突かれた。
口に入れると3種ともすべてセビーチェだったからだ。
おそらく、見た目も味も異なる3種のセビーチェという解釈で良いのだと思う。
本ミル貝と海ぶどう、次は赤貝をおぼろ昆布で包んだもの、そしてホッキ貝のセビーチェ。
セビーチェは、白身魚と玉ねぎやトマトをレモンや塩で味付けしたペルーの伝統料理だ。
食材の選び方やマリネの仕方によって、千差万別のセビーチェが生まれる。
ちなみに、このときのペアリングのドリンク(ノンアルコール)は岩海苔ベースのベルガモットと柚子を加えたカクテル。
セビーチェを食べた後に飲むと岩海苔の香りだけが消えて、ベルガモットと柚子の香りのドリンクになるのは新鮮だった。

②海岸砂漠 85MASL(海抜85m)
ホタテ – カボチャ – ウニ
黄色と緑の料理。
かぼちゃの皮(おそらく)を練り込んだ生地の中に焼いたウニが入っている。

③海岸線 0MASL(海抜0m)
桜エビ – ロコト・ペッパー – 大根
ベースはタイガーミルク。タイガーミルク(虎のミルク=レチェ・デ・ティグレ)とは、魚介やタマネギをマリネした際に出る液体部分のことで、現地では二日酔いのときなどに飲むという。ここでは、そこに生のボタンエビと唐辛子ロコトを加えている。

⑤海霧 -15MBSL(水深15m)
イカ – ホタルイカ – イカ墨
網は細いポテトのような何か。細く作って干して食べられる網にしてある。
網の上には網に捕まったホタルイカ(軽く火が入っている)。
網の下にはイカと”のれそれ”、イカ墨のソース。

⑦アンデスの森 3260MASL(海抜3260m)
鹿 – トウモロコシ – 山菜
山菜を現地の食べられる土で成形したワティアの中に詰めて蒸し焼きにしている。
通常はイモなどを入れるそうだが、このときはそら豆のさやに詰めた山菜が提供された。
「マス」の料理の最大の特徴は、料理それぞれが「ペルー料理を」ではなく「ペルーを」感じさせるところだ。
「ペルーの自然や生態系をゲストに想起させる」と言い換えた方が近いかもしれない。
コースにはもちろん、セビーチェやワティアなどのペルー料理(と技法)、また、唐辛子ロコトなどペルーならではの食材が用いられるのだけれど、食べている際にペルーを感じさせるのは「料理」よりもっと基層に位置する味覚や食感、食材の組み合わせからなのだ。
行ったことのない国を感じさせる。ペルーを訪れたことのない私にとって、それは意外な感覚だった。
たとえば、アミューズ「冷たい海 貝 – スピルリナ – 海ぶどう」は、味覚としてのセビーチェを感じさせるし、「海岸砂漠」の焼いたウニは、そのもそもそした食感から、おそらく水のない砂漠をイメージさせている。
味や食感を抽出してペルーを表現する手法は、本国セントラルとは異なる東京独自のアプローチではないだろうか? なぜなら、ペルー料理をよく知っているはずのセントラルのゲストには、味でペルーを感じられるのは自明であり、それならば、料理を通してもっと別に伝えたいことがあるはずだからだ。
だから、そのコンセプトを日本独自にどう展開するかを日々考え、独自の料理に落とし込んでいるフェルナンデスさんの実力は、ただものではないと思わせる。
さらに料理全体から感じられたのが、ある種の純粋性(ピュアネス)のようなものだった。
それは、上に記したような「コンセプトが忠実に料理に再現できている」完成度とはある種対照的に感じられる、どこか、たどたどしいような素朴さだ。
網に捕まったホタルイカを視覚的に表現した「海霧 -15MBSL」は、細いポテトか何かで作られたラフな網の下にホタルイカとのれそれがあり、より自然に近い視覚的イメージを持っている。
雑味のない日本の食材であることも、それを後押ししているように思う。
そして最も重要なのが、それらのコンセプトを脳内からすべて捨象してしまってもなお、料理が単純においしいことだった。
冒頭でご紹介した「セントラル」の研究機関「マテル・イニシアティバ」に、在籍していた日本人がいる。文化人類学者の藤田周さんだ。藤田さんはリマの「セントラル」と「マテル・イニシアティバ」に併設されたレストラン「ミル」の両方で料理人として働きながら、異質な文化・社会を体感的に理解するという、文化人類学的フィールドワークを約2年間行ってきた。
藤田さんは、過去に行われた講演で、「セントラル」の中の人たちの味覚の考え方について紹介している。
「セントラルは自身の、また客のおいしさの感覚を拡張することを試みることがある」
(「おいしい未来研究所」公開講座 2022.11)
料理が必ずしも従来のおいしさからはおいしいとみなされるものでなかったとしても、おいしいものとして提示することを目指すときがあるという。
藤田さんはその例として、乾燥ジャガイモのチューニョという食材をチップスに練り込んだことをあげていた。独特の香りから敬遠する人の多いというチューニョを「おいしいと思うようになることを望んでいる」というのだ。
味覚としてのおいしさを担保しつつ、ゲストが知る「おいしさ」を拡張すること。
そのチャレンジの姿勢にこそ、「セントラル」の、ひいては「マス」の本質があるのだろう。

「セントラル」では、シェフ・マルティネス氏を含むスタッフが先住民の植物や根菜、海藻のサンプルを集め、これらの自然の恵みをメニューに織り込み、自分が体験した自然について語るという。
それは東京の「マス」でも同じだ。
マルティネス氏の世界観と「マテル・イニシアティバ」のモットーである “Afuera hay mas”(外にはもっとある)にインスパイアされた「マス」。
エントランスにはペルーの食材が飾られ、ゲストは料理ごとにその料理が表現する自然環境をイメージした小さな紙を手渡される。BGMにはペルーで採集した自然界の音が流される。
「マス」を訪れる私たちは、9皿の料理を通して新しい味覚に触れ、彼らの語る物語に耳を傾ける。
そして自分自身の五感を通して新しいペルーを知るのだ。
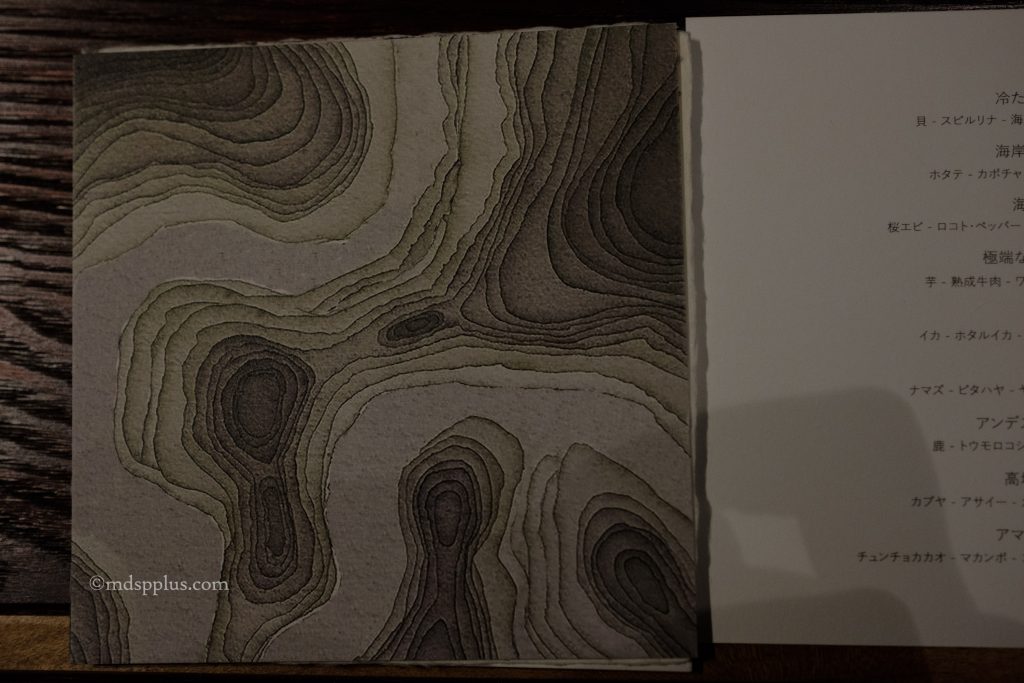
「MAZ(マス)」
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町3F
03-6272-8513 (15:00-17:00)
https://maztokyo.jp/
席数 20席
営業時間 17:00〜23:00
定休日 火