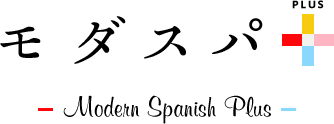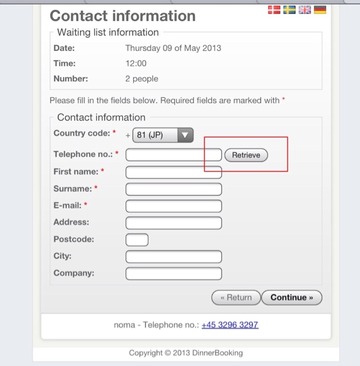今年の夏もまた北欧にやってきた。
今回の訪問はアイスランド、フェロー諸島、ミキネス島、ボーンホルム島。
8月の北欧は日没が遅く、たそがれどきの夕暮れが長く続く、良い気候だ。
レストランはolo(ヘルシンキ)、KOKS(フェロー諸島)、KADEAU(ボーンホルム島)。

フェロー諸島に飛ぶ前に、ムーミンとマリメッコの国フィンランド、oloのあるヘルシンキに立ち寄った。
oloはヘルシンキ市街地から近く、ヘルシンキ港の目の前にある。
港のにぎわいと夕暮れに照らされた夏の夕方のダイニングは、19時でも店内の照明より外の光の方が強かった。

予約したのは、煌々と明るいキッチンをのぞき込むような2席のカウンター。
oloにはシェフズテーブルならぬシェフズカウンターが2人席で2か所あり、キッチンでの様子が手に取るようにわかる。
料理はコース1種類のみ。
Part1
Almond and cauliflower
Oyster with wood sorrel
King crab and radish
Finnsh beef and Kohlrabi
Goat cheese with raspberry
Sterling white halibut eith Icelandic wasabi
Part2
Scallop from Norway and mussel jelly
Chawanmushi,tomato and dashi from smoked reindeer heart
Part3
Bread serving
Reindeer calf liver with strawberry and beetroot
Part4
Cod from the Nortn Sea poarched in grilled butter and summer vegetables
Emmer semolina and browned butter
Part5 optional
Cheese plate
Part6
Berries and meadowsweet
Spruce and bilberry
Hommage a la patisserie

Oyster with wood sorrel
最初は牡蠣。
軽くスチームされている。レモンの代わりの軽い酸味にソレル(スイバ)という感じ。上の白い小さな玉はホースラディッシュを冷たいジェラート状にしたもの。
このあとのフィンガーフードも、ゴーダチーズやキングクラブにフィンガーライムなど、どれも味のベースが酸味だ。
フィンガーフードは3種類出てきて、柔らかな酸味のものから、口に入れた瞬間に「すっぱ!」と言いたくなるものまで、おそらく意図的に酸味の強さや方向性を変えている。

Sterling white halibut eith Icelandic wasabi
ハリボー(オヒョウ)。
北欧で魚料理となると、タラとこのハリボーが最もポピュラーだ。

ホースラディッシュの代わりにアイスランド産のわさびが出てきたのは驚いた。
おろすのは日本の鮫皮おろし板。目の前で摺り下ろしてくれる。
形状も日本のわさびとそっくりだ。
アイスランドのわさびは日本産より香りがやさしく、わさびだけで食べられるほど辛味もやわらかい。
もし醤油と合わせたら、醤油の香りに負けてしまいそうなほどだ。
香り付けしたオイルと調味料の差し込み加減が細かい。
調味はオイルが主体でわずかに軽い酸味。バルサミコのような感じ。
イタリアのカルパッチョと同じ構成。そこにわさびが入ると、どうも軽い醤油の風味に感じてしまうのは錯覚か。
トッピング花の香りも効いている。紫蘇の香りに似ていると感じる。これも習慣による錯覚かもしれない。

Scallop from Norway and mussel jelly
ノルウェーのホタテとムール貝。
上にこちらもソレルが見える。泡の下には若いグースベリーのような実が入っていて酸味を足していた。ここでもやっぱりポイントは酸味だ。
個人的には、ホタテの焦げの香りはなくてもよかったような気もする。

Chawanmushi,tomato and dashi from smoked reindeer heart
茶碗蒸し。軽い、青い香りのオリーブオイル。
日本語圏以外の人には説明するのかな。
香りは軽いがテクスチャは重い。
茶碗蒸しの上部は、セミドライトマトといくらとスプラウト。
だしはスモークしたトナカイの心臓でとっているらしい。
このあとにも何品かトナカイの料理が出てくる(後述)。
こちらのオーナーのヤリ(Jari Vesivalo)さんは先ほどのわさびもそうだが、日本の料理がお好きのようで何度か来日もしており、2016年には日本でコラボディナーもおこなっている(東京・広尾の「Ode」と静岡・富士宮の「レストランビオス」)。
このときはいらっしゃらなかったのであとで伺うと、何度かの日本旅行で日本が気に入って、料理にも日本のエッセンスを取り入れているのだそうだ。
ここでの日本料理は単なる真似や料理の引き出しを広げるパーツではなく、もっとこなれてモダンノルディックのひと皿として成立していると感じた。
私はモダンノルディックを現地で食べ始めたのが2010年なのでまだ10年経っていないが、その変化・進化は毎回眼を見張るほどだ。

Reindeer calf liver with strawberry and beetroot
トナカイの肝臓を、フォアグラのテリーヌのように仕立てている。
ストロベリーのジュレとビートルートのマリネとソレル。
かなり挑戦的。印象には残るがそれは、単純なおいしさではない。
端的に言って血なまぐさい。
血なまぐささをベリーの甘みと酸味でマスクしている。それは理解できるが、それでもなおマスクしきれない生臭みは感じられる。
この、昔ながらの、あるいはありのままの肉の加工は、このあと訪れたフェロー諸島のKOKSとボーンホルム島のKADEAUにも共通していた。
「おいしくない」と片付けるのは簡単だが、調理器具や流通の進展でおいしくすることが昔より容易になった今の時代、あえてそうでないものにするのは「わざと」だろう。しかも行った3軒すべてだ。
しかし、トナカイの肝臓は処理でもう少し生臭さは取れそうなものが、そうなっていないのは不思議ではあった。

Cod from the Nortn Sea poarched in grilled butter and summer vegetables
北海のタラ。
軽く火を入れて、ヘーゼルナッツオイルでまとめている。
夏の野菜が色よく配置されている。

Emmer semolina and browned butter
これがいわゆる肉料理ということになるのだろうが、メインの食材についてメニューに書いていないのはわざとだろうか?
上はトナカイの心臓の節を削っているらしい。
鰹節を削ったような食感と肉のうまみがある。
これは先ほどのトナカイの肝臓とは異なり、食べやすい。
「茶碗蒸し」の料理もそうだったが、この「トナカイ節」を、ここでは、日本の鰹節のような感じでだしを取ったり食材として用いたりしているらしい。
全体で気づいたことをいくつか。
oloの料理は、全体的に料理の見た目は明るく、テクスチャは全体的に軽く、食べやすく(トナカイの肝臓を除いて)、プレゼンテーションが都会的に感じられた。
しかし味付けは意外と塩や酸味がしっかり載っていて、例によって見た目と味の濃さが一致しない。
いまどきのモダンノルディックの典型的な料理だ。
酸味をけっこう強く当てる。
塩味も強め。
酸味は、柑橘の代わりに、たくさんのベリー類やソレル類を使っている。
oloの料理は、タラのヘーゼルナッツオイルやハリボーとわさび、”トナカイ節”など、細かい組み立て、パーツの小さな料理だ。これはモダンノルディック料理全体の特徴のひとつといっていいかもしれない。
食材のパーツの小ささは、味の破片が多く、それが味の複雑さになり、繊細な印象を生む。
しかしともすれば、このパーツの小ささと複雑さが、モダンノルディック料理を好まない人からときに「食べた気がしない」と言われてしまうゆえんでもあるだろう。
oloの料理のプレゼンテーションの特徴として、一つ一つのポーションが小さく、また、盛り付け方が縦に積む方式が多いことに気づいた。
料理はいずれも、細かいパーツを上下に繊細に重ねることでできており、柔らかい食材が多い。
「盛り付けが縦」というのとき、平たい皿に平べったい素材を高く積み上げる方法もあるが、ここでは、半径が小さく深いつぼ型の器が多かった。
ゲストは自然と、それをのぞき込んで食べる姿勢になる。
メイン食材を隠して上に葉っぱなど別の食材を置くのはなぜかモダンノルディックの料理に多く、これはそのバリエーションともいえる。
この方式だと、下にある食材は見えず、最初の見た目ではどんな料理であるかの全貌がつかめない。(「茶碗蒸し」も、下のフラン部分ははじめ全く見えなかった)
何かわからないものを慎重にスプーンでかきわけていく動作は、自然と、ゲストの料理への没入感を生む。
みんなでシェアしながらわいわい食べる料理ではなく、めいめいが自分の皿の中に神経をそそいで食べる料理。
食べるときの精神のもちようが、料理の盛り付けにも表れるものだなと思う。
盛り付けだけでも食べた印象は変わるものだ。
2004年にデンマークのクラウス・マイヤーを中心とした料理関係者の間で提唱された例の「10か条のマニフェスト」。
その中に、「外国の影響をよい形で取り入れ、北欧の料理法と食文化に刺激を与える」という項目がある。
例えば先ほどのハリボーのカルパッチョも、わさびとオイルの組み合わせが単なる日本料理っぽさを越えて、モダンノルディックのひと皿になっていた。
これは日本人でなければ、日本の影も気づかないくらいだろう。
随所に入っていた日本を思わせるパーツは、取ってつけたような感じでなく、料理の必然として自然に入り込んでいたり、さらにそれをひねっているのが印象的だった。
7年くらい前に北欧の某店で、「鰆の西京焼き」そのまんまみたいなのが出てきたのを思い出す。
ベスト50世界で何位というような店でこれはないだろうとそのときは思ったが、これは個々のお店の能力というより、どの店も、時間を経てこなれてきたということではないかと思う。
発祥が比較的新しく自由なモダンノルディックは、他国の料理のエッセンスを取り込みやすい。フランス料理のような、元となる伝統料理が少なく、作る人の個性が料理に反映されやすいのかもしれない。
今後も大きく変わっていく要素を多く含んでいる。
しかもそのスピードが、加速度を増しているように感じられる。
oloも来年、再来年行ったらまた変わっているのだろうなと思いながら店を出た。
年を追うごとに急速に進化していく料理をこれから追うことが出来るのは、それを見ているいまの私たちにとっても今後どう変わっていくかわからない、エキサイティングで幸せなことなのだ。

Restaurant Olo
https://olo-ravintola.fi/en/
+358 (0)10 320 6250
Chef Jari Vesivalo
Pohjoisesplanadi 5
00170 Helsinki
Finland