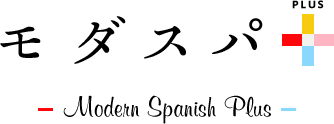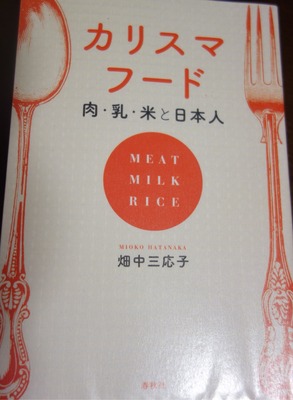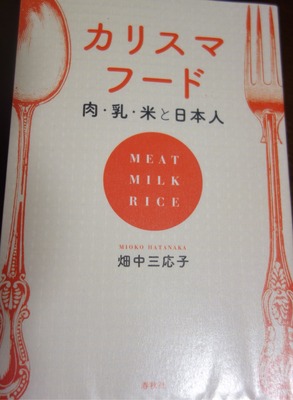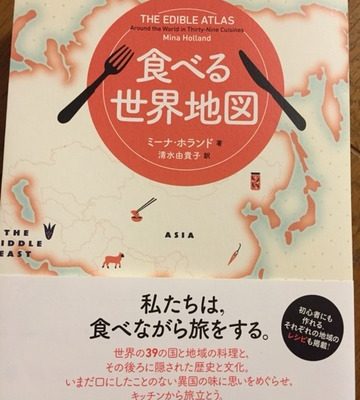私たちが日々、何を食べるか決めるとき、何を判断材料にしているのだろう。
それは以前ちらっと目に留まった週刊誌の見出しであったり、コンビニで見かけた雑誌であったり、おいしかったよという友人とのおしゃべりだったりする。
流通は保証され、食のタブーもそれほどない。レストランだって選択肢がいくらでもある現代の日本で、食べることの判断材料となるのは情報だ。
書名の「カリスマフード」は著者の造語。
単なる食べ物という域を超えて、カリスマ的な存在感を持ち、国の食糧政策や時代と深く関わってきた肉、牛乳、コメに対する、著者の敬意と複雑な思いがこめられている。
本書で特に著者が注目するのは、牛肉や牛乳が日本国内に導入され定着していく過程で、メディアなどの情報や国の政策に大きく振り回されて、忌避されたり逆に熱狂的に受け入れられたりという振れ幅が激しかった点だ。
例えば牛肉。
肉そのものは、いまから150年前の文明開化で肉食が解禁される前からも、獣肉全般を「山鯨」、イノシシを「牡丹」、シカは「紅葉」と呼び、ももんじ屋と呼ばれる牛肉店が江戸期から繁盛していたように、日本人は古来から肉を獲って食べてきた。
明治期に、日本在住の外国人が牛肉を食べるために牛を屠殺する必要が出てきて、江戸(現在の港区白金台付近)に屠殺場として畑が提供されたものの、付近住民の苦情が強く、屠殺は数頭しか行われなかった。
その理由は「村が穢れる」というもの。
これまでのシカやイノシシよりずっと大きな牛の屠殺には抵抗が大きく、牛鍋屋も、できた当初は閑古鳥が鳴いていたという。
それが一変して牛肉ブームになるのは、明治天皇が牛肉を食べた記事が報道されたこと。
当時の明治政府では欧米の科学と医学を全面的に取り入れ、西洋の「すぐれた」文明に追いつき、日本人の体格を向上させることが国策となった。
そしてそのころ、外交の正餐にフランス料理が取り入れられた。
本書には1871年(明治4年)11月に外務省が天長節を祝して在日外国人高官を招いて饗応したフランス料理の献立が掲載されており、そこでもマデラ酒ソースがけのローストビーフや、牛フィレ肉のペリゴール風など、現代につながる料理が作られていたことがわかる。
そういう、天皇の食事や外交での料理に使われるような権威付けや、富国強兵策に伴う軍隊への牛肉導入などが、牛肉がそれまでと一転してブームとなっていく。そして例の「牛鍋食はねば開化不進奴(ひらけぬやつ)」(仮名垣魯文『安愚楽鍋』)という名文句が出てくるまでになるのはご存知の通りだ。
一方で牛乳では、病人や子どもに与えて病気を治すというところから、母性的なイメージを与えられて普及していく。
富国強兵の男性的なイメージがついて流布した牛肉と対照的だ。
その大きなきっかけとなったのが「完全栄養食品」ということばだ。
このことばは、1892年(明治25年)に出された育児書に「牛乳は実に人乳によく似ていて、十分完全な滋養物」と書かれているあたりから始まったという。
それが戦後直後の1946年の栄養の基礎知識を述べた書物になると「牛乳はすべての栄養素を完備した栄養食品である」と単純な言い切りになっており、このシンプルさが、牛乳が完全栄養食品として本格的に普及していくきっかけだったのではないかと述べられている。
国を挙げて導入がおしすすめられ、最初はなかなか浸透しなかった牛肉や牛乳が、その後ブームといえるほどに普及したのは、日本人全体の傾向と切り離せないだろう。つまり、外来の食べ物に弱く、欧米に対する熱い憧れがあり、さらには欧米コンプレックスと「追いつけ、追い越せ」の敵愾心。
著者はその日本人の精神に寄り添う一方で、上からの押し付けにもちゃっかり乗って、牛鍋屋を開業させてしまうような庶民のバイタリティや柔軟さにページを割くことも忘れていない。
本書を読んで見えてくるのは、食のめまぐるしい変化を通して浮かび上がる、日本人の自画像なのだ。
カリスマフード 肉・乳・米と日本人
畑中三応子 著
春秋社(2017年1月)
本体1,900円+税
ISBN:978-4-393-75124-4