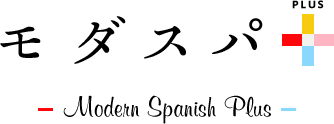(2020.9.2追記)特集内の「皿を跳躍するイマジネーション」が生まれた背景を、高田裕介氏に訊きました。↓文末に追加しています。
東京都に緊急事態宣言が発表され、レストランはおろか日常生活すべてが大幅に制限された今年前半の数か月。
現在は緊急事態宣言もいったん解除され、経済を回すことと感染症拡大予防を現実的な路線で天秤にかけながら、私たちの行動範囲はある程度広げることが可能になり、レストランでの会食も徐々に行われるようになってきた。
日常の行動はそうやってある程度以前に近い形で戻ってはきたが、それは決して、コロナ前の世界に戻れることを意味しなかった。
コロナ禍で今年前半に数か月単位で店を閉めざるを得なかった人たちは、テイクアウトや通販営業、ケータリングに一時的に転じるなかで、レストランという空間でしかできないことについて考え直すきっかけを得た。
休業せざるを得なかった数か月の間に、多く生まれた自宅での時間。
その長い時間に自分自身に向き合った人たちの言葉が少しずつ、まとまった形で雑誌媒体などで読めるようになってきた。
「専門料理」(柴田書店)20年9月号では「五感 心を揺さぶる料理とは」と題した特集を組んでいる。
レストランとは何か。いまレストランでこそできることとは何なのかを改めて問う試みだ。
「五感」とは、視覚・味覚・嗅覚・聴覚・触覚の五つ。
特集ではこれらを「レストランでしか体験できない高揚感」を演出するための要素としてとらえ、レストランとして前に進むためのさまざまなヒントを提示している。
特集から読み取れることは、簡単に言えば、以下の2つ。
①時間と場所を共有することによってしか得られないことは何かを問い直す
②ゲストの食べることへの固定観念を揺さぶり、ひっくり返す
これを洗練された、そしてかなり極端な形で誌上で見せてくれたのが「LA CIME」の高田裕介氏だ。
「皿を跳躍するイマジネーション」は、誌上のビジュアルだけでもかなり刺激的だ。
メニュー表をぐちゃぐちゃに埋め尽くした食材の名前。
鳥かごの中に鎮座する料理(どこから開けるんだ?)。
そして究極的には、手をつっこむ穴だけが空いた、中の見えない黒い箱。料理が入っているのかすら不明。
ビジュアルは実際に誌面を見ていただければと思うのだが、これら、もう料理にすら見えない何かは、高田氏が「レストランではお客様に気持ち悪さを感じさせる要素はタブー」などの常識をあえて破ってみせた実験作だ。
そこから逆説的にレストランの料理に必要なものは何なのかが見えてくる。
それを切り分けるために、高田氏は食べる楽しさ、料理を想像する楽しさ、人と集う楽しさをすべて飲食からいったん切り離して誌上で再現してみせた。
「万人に好かれることをめざさず、ひたすら自身のクリエイションにまかせて作った料理」の先進性は、見る者の興味をかきたててやまない。
そしてさらに衝撃的だったのが、高田氏の次の発言だった。
「皿の上だけで料理を考える時代はもう終わった」
そのこころは、料理人はこれまで「いかにおいしいものを作るか」だけを考えていればよかったのが、それだけでなく、これからは「いかにゲストを楽しませるかという部分も含めて考える必要がある」という意味のようだ。
考えてみれば、現在のレストランをめぐる状況は確かに、いやおうなくそうなってしまっているのだ。
突然レストランを休業しろと言われ、再開したらしたで時短営業しろと言われ、しかも席間を離して、人との距離をとって、大きな声で話すなと言われれば、レストランの楽しさはかなり削がれてしまう。
さらに高田氏の言う通り、対面する楽しさに代わるインフラがある程度整っていたことが皮肉にも、私たちに、空間を超えて集えるという新たな便利さに気づかせてしまった。
(10年前ならこうはいかなかっただろう。通信のインフラはまだ脆弱だった)
いまは実際に会わなくても、ある程度「なんとかなってしまう」のだ。
そんな時代に、レストランでしかできないことを突き詰める――。
五感を通して思考することをレストランの新しい楽しさにしたいと、高田氏は語る。
そもそも食べるのは本能にもとづいた快楽であったはず。それなのに「思考すること」を求められると面倒くさいと思うかもしれない。
それをあえて高田氏は「楽しさ」と言う。
固定観念のリセットが必要とされているのは、作り手も食べ手も同じなのだ。
テイクアウトやケータリングでも足りる時代に、私たちがあえてレストランに足を運ぶために。
今回の新型コロナウイルスの感染症拡大の問題の特徴は、世界でほぼ一斉に、全く同じ災いが「平等に」降りかかってきたことにあると思う。
コロナ禍を乗り越えなければならないという命題は、レストランも食べ手も同じ。
こんな「平等な」災い(といってよければ)は、これまで世界で体験されたことがなかった。
この、先が誰にも見通せない状況を見ながら進むという時点で、元の世界に戻れるわけがないのだ。
著述家・翻訳家の関口涼子氏は、先日の朝日新聞(8/29付「ひもとく」)で、コロナ禍で失われつつある自分を取り戻すために必要なのは五感の復活だと述べる。そこでシャンパーニュ醸造責任者のエルヴェ・デシャン氏など、五感を通じて自然と人間をつなぐ仕事をしている人たちのの例を挙げ、彼らの共通点を次のように説く。
「多くの職人は、五感を鋭敏にし、世界が与える豊かさをものという形で私たちに受け渡しているのだとはいえないだろうか」
五感を通じて自然と人間をつなぐ仕事――料理人という仕事も、まさにその役割に当てはまるのではないかと思った。
そしてまた関口氏はこうも述べる。
「同じ物を食べても、他人がどう感じているかはわからないように、五感は基本的には個人的なものだが、言葉を通して初めて分かち合いが可能になる」。
五感を鋭敏にすること。そこで受け取ったものを分かち合い、つなぐのはことばなのだ。
レストランの料理とは人が作るものであり、それを受け取るのも人で、その楽しさを分かち合うのは言葉だ。
人との接触、場の共有が希薄になったいま、人々がつながるために必要なものは、場を分かち合うための想像力であり、また言葉なのだということを、私たちは再び思い返すべきなのだ。
(2020.9.2追記)
高田氏は、この特集内で「皿を跳躍するイマジネーション」をテーマに6つの料理を試作、誌上で再現した。あの誌上の料理が生まれた背景を高田氏に聞いた。(公開については高田氏の了解を得ています)
――あの料理、極端だけどレストランとして考えなければいけない要素をたくさん含んでいて、興味深く読みました。あれはどうやって考え出されたのですか?
高田 今回の特集内容の一部は、実は数年前から頭にあったものなんです。
だから「今回は自由にやってください」って編集の人から電話依頼が来たとき、アイデアはすぐに思いついたし、日頃考えていたことが自由に言えると思って、電話口でたくさんしゃべっちゃいました。
話しながらアイデアがばーっと浮かんでくるのが久し振りで楽しかった。柴田書店さんに感謝です。それで、その電話中に描いたのがあのイラストです(注;特集61Pの「MAKING NOTES」)。
――すごい!早描き!しかも、あれでほとんど完成形じゃないですか。
高田 特集を依頼される前は、実はとてもあんなことを考えられるような心境ではなかったのですが、みんな今の(コロナで休業要請が出ている)このタイミングでしか、自分の料理について考える時間はないんじゃないかと思いました。
みんなそもそも技術力はすでに高いんだから、ビジュアルはもういい感じじゃないですか。だから、今回は僕の(誌上の)料理を見てもらって、それをきっかけにして、素材とかご自身の感覚を深掘りしていって欲しいというのが僕のメッセージです。そのヒントになればいいなと思います。
結果的に表現が少しオーバーになったところもありましたが、ページも当初予定より増やしてもらって8ページもらえてありがたかった。
――あの写真はカメラマンさんの撮影ですか? ご自身の撮影?
高田 カメラマンです。
スモークとか炊いて欲しかったけど(笑)
――スモーク(笑)黒い箱の料理ですね。真っ黒で逆に禍々しさは伝わりましたよ。これ、まだお店では出してないんですよね?
高田 出してないです。うちはまだまだご飯屋さんです。僕も美味しいのが好きなんで。